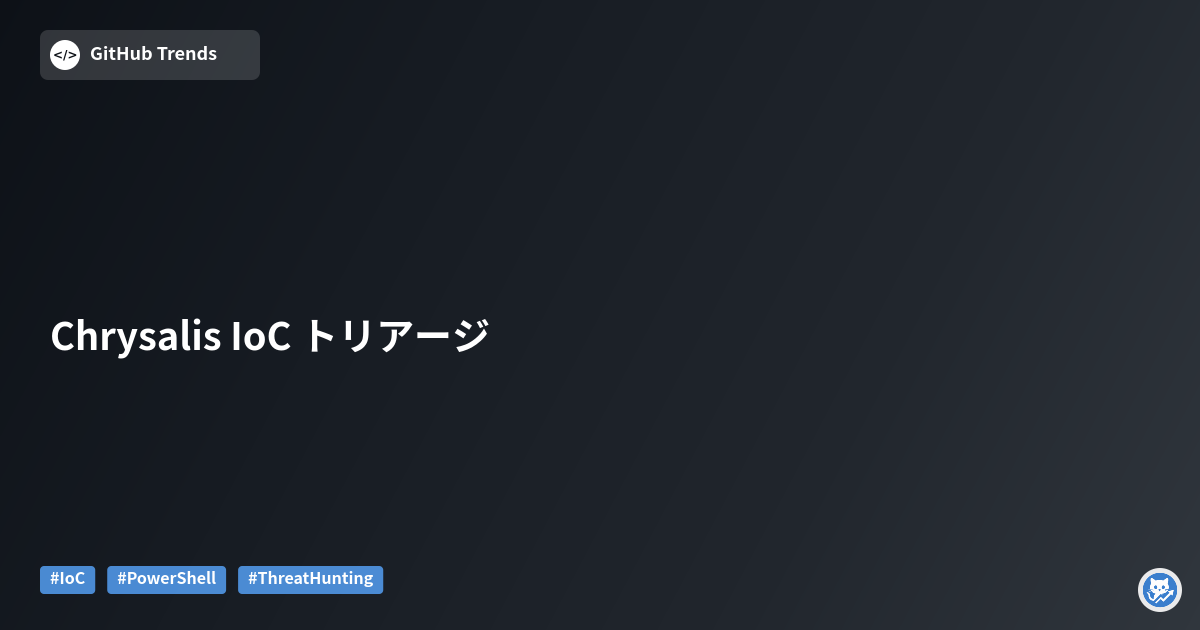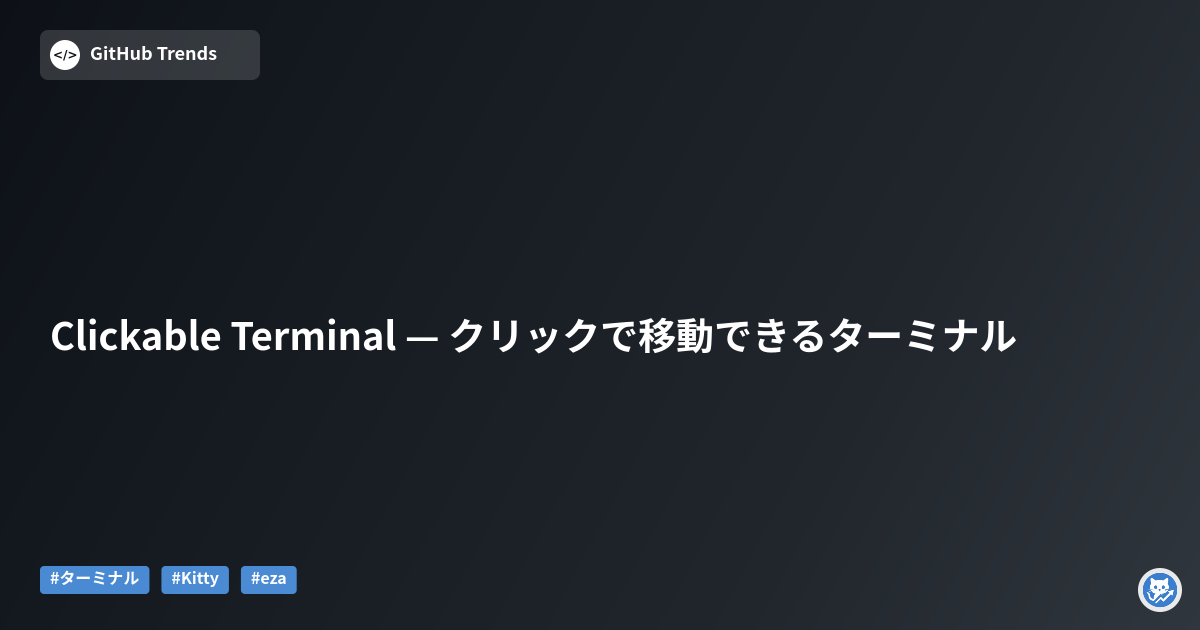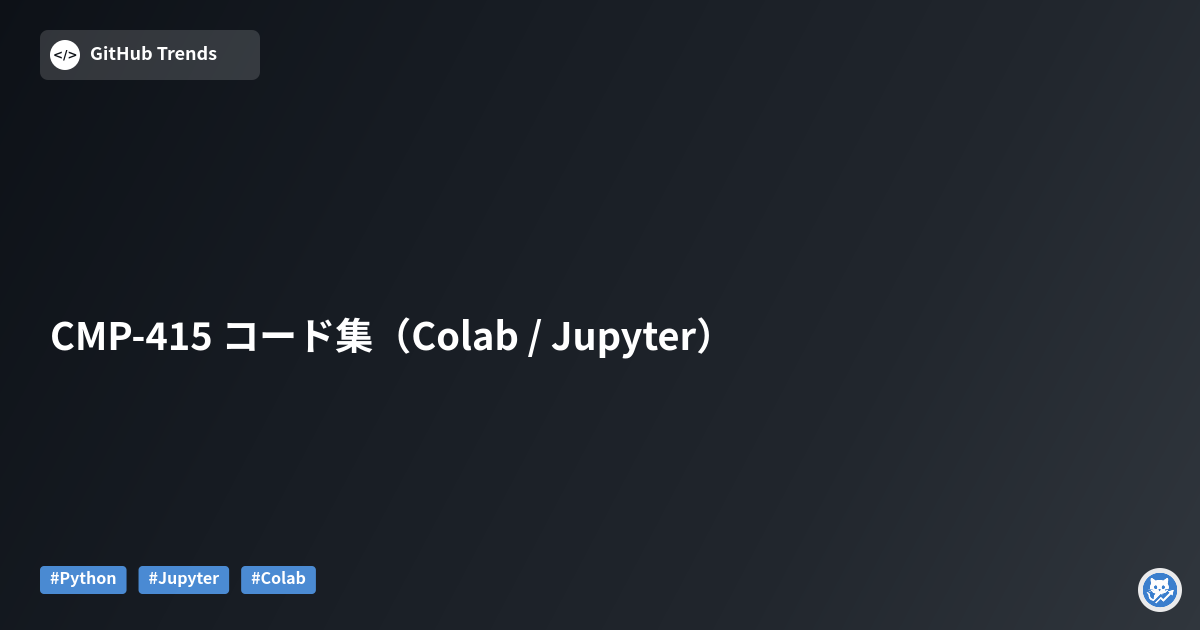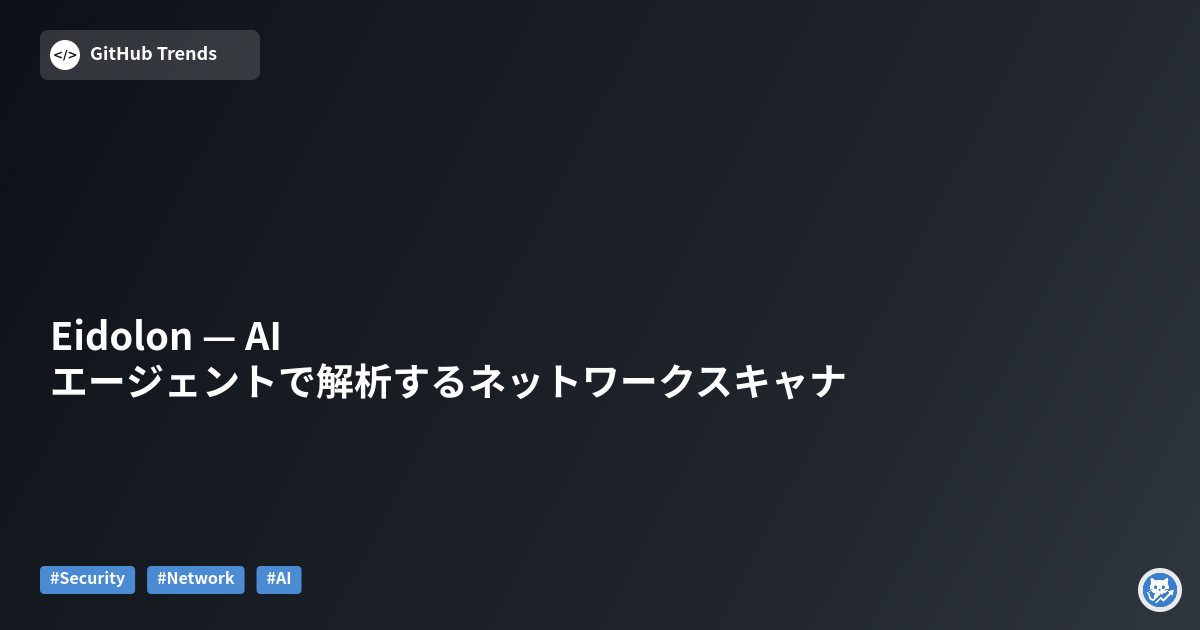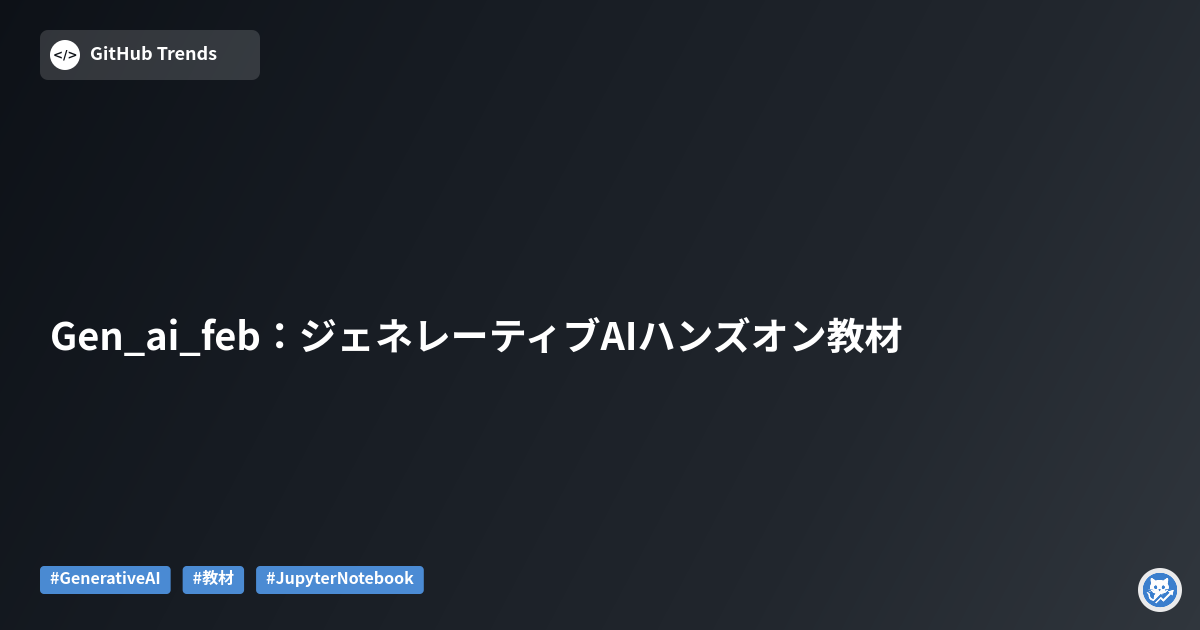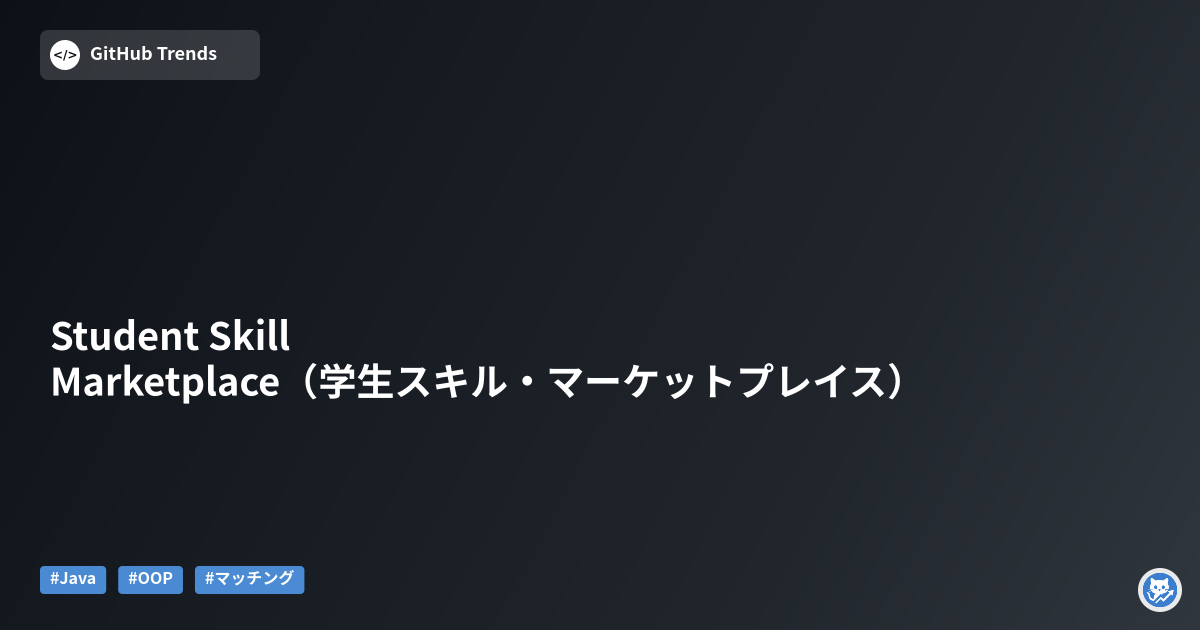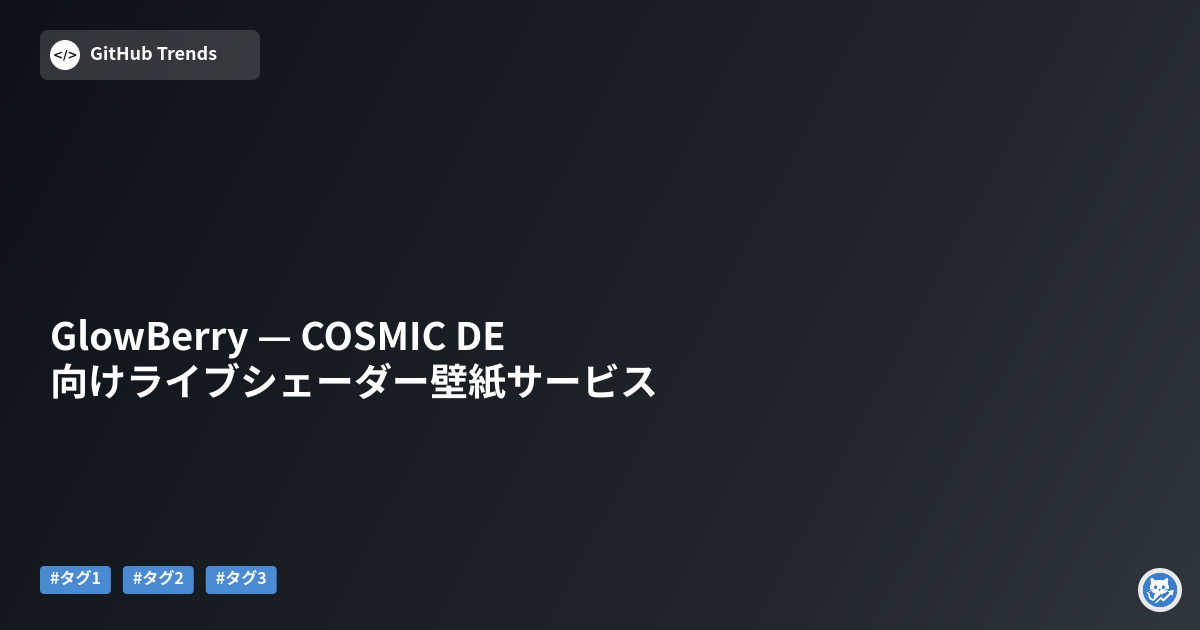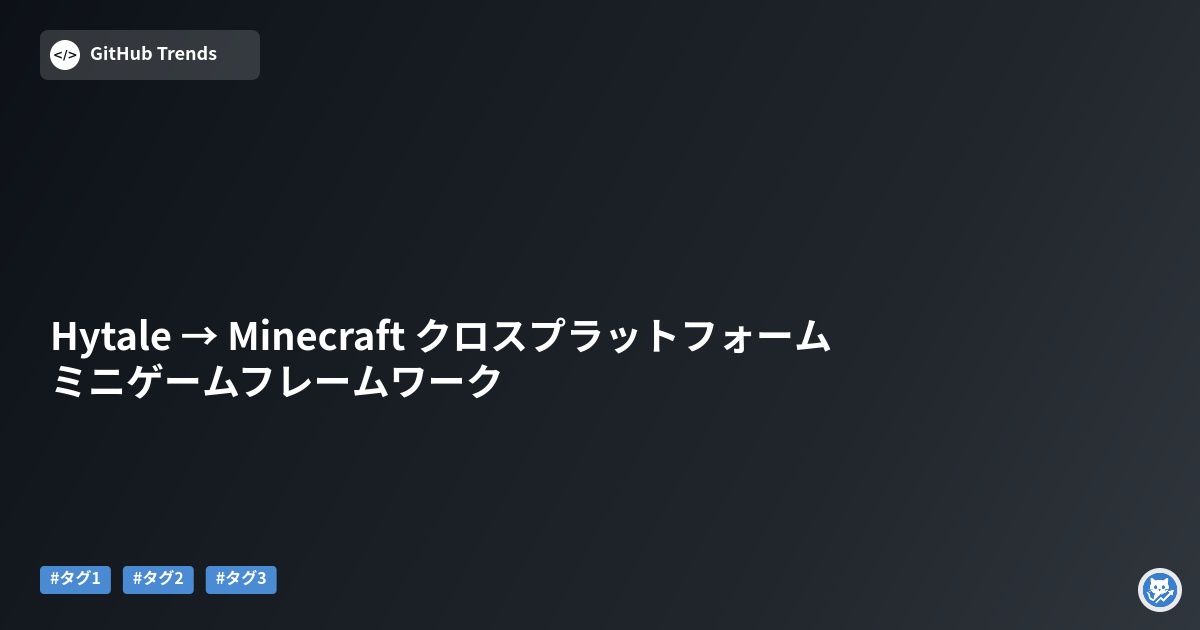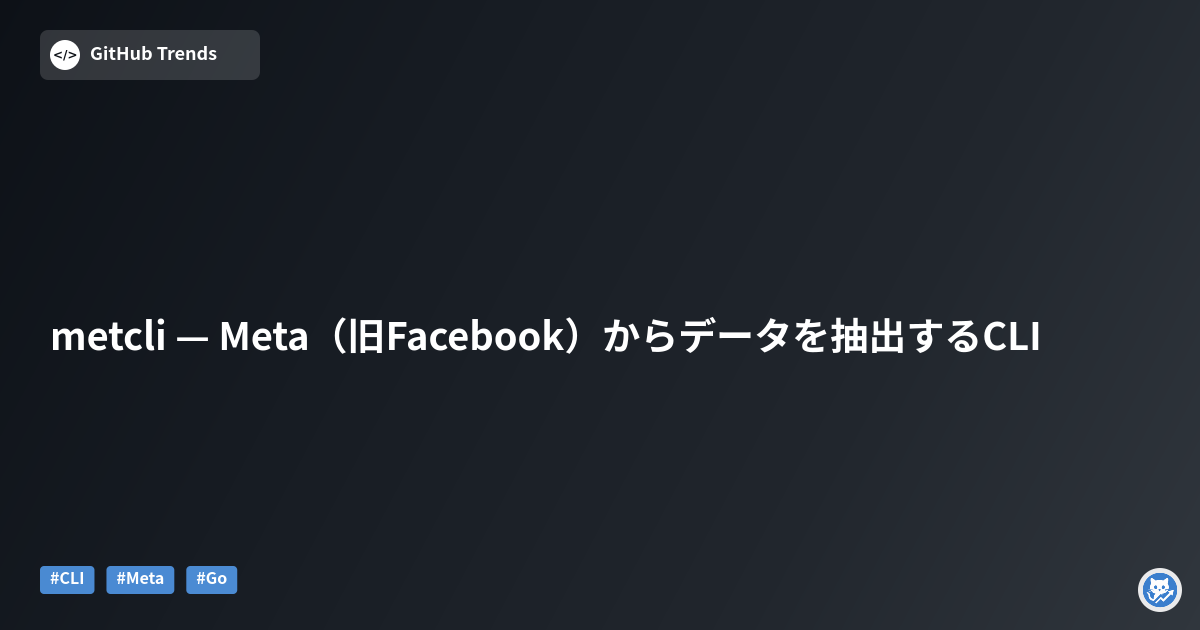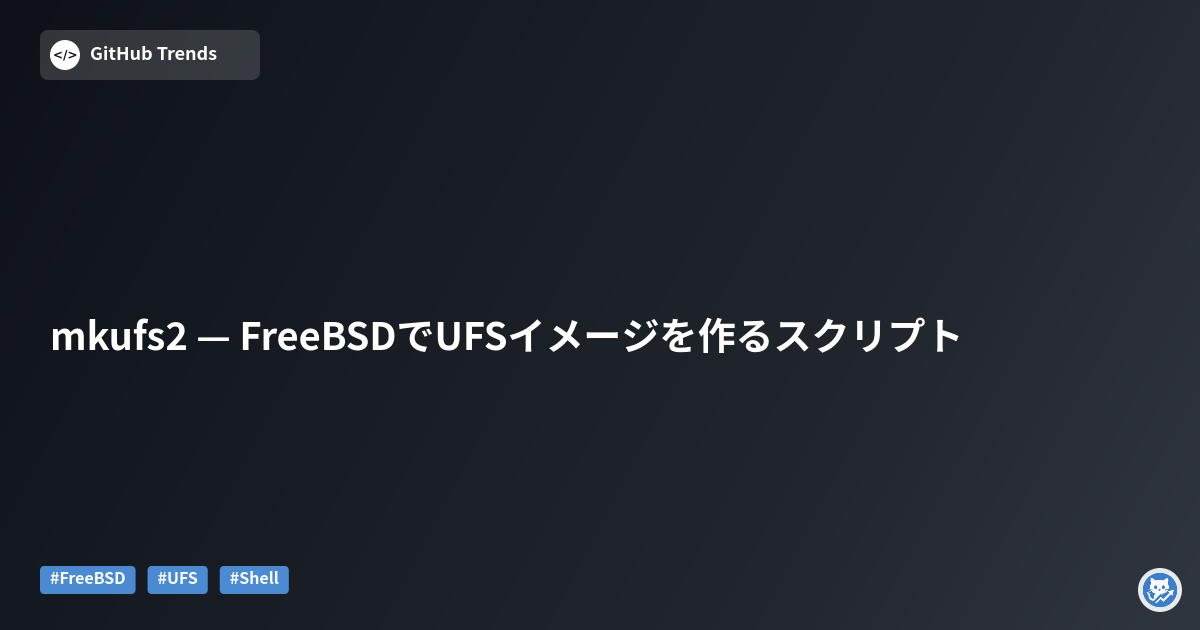CapCut Pro Tools 2026 — 非公式ツール集
2026/2/3
CapCut Pro Tools 2026 は、動画編集アプリ「CapCut」の有料またはプロ機能に関連すると推測されるツール群を想定したリポジトリです。現状はファイル数が少なく(README と LICENSE のみ)、実装コードや言語指定はありません。スター数は一定の注目を集めている一方で、実用的な成果物やドキュメントは限定的で、拡張や検証が必要な段階にあります。本記事では現状の構成と技術的観点、今後の展開案や注意点を整理します(約300字)。